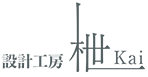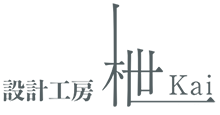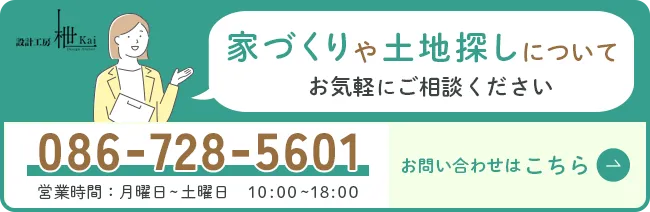「2025年の建築基準法改正で、リフォームが今までよりも厳しくなるらしい…」そんな話を耳にしたことはありませんか?特に「4号特例の縮小」によって、小規模な建物でも審査が必要になるケースが増え、これまでスムーズに進んでいたリフォームが時間やコストの面で影響を受ける可能性があります。
では、この改正によって具体的にどのような影響があるのでしょうか?
今回の記事では、2025年の建築基準法改正がリフォームに与える影響や、スムーズに進めるための対策について詳しく解説します。改正前後のメリット・デメリットを比較し、費用を抑える方法についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

2025年建築基準法改正とは?
2025年4月、建築基準法が改正され、増築やリフォームにおける手続きが大幅に変更されます。特に注目すべきポイントは、「4号特例の縮小」です。これにより、これまで建築確認申請が不要だった木造2階建て住宅のリフォームや増築でも、申請が必要になるケースが増える見込みです。
今回の改正は、耐震性能の向上や省エネ基準の強化を目的としており、より安全で環境に配慮した住宅の実現を目指すものです。一方で、申請手続きの増加により、工事スケジュールが長引いたり、予想以上のコストがかかる可能性もあります。
そのため、スムーズにリフォームを進めるためには、改正の内容を正しく理解し、どのような影響があるのかを事前に確認しておくことが重要です。ここでは、改正の背景と目的、そしてリフォームに与える影響の全体像について詳しく解説します。
改正の背景と目的
今回の建築基準法改正の背景には、建物の耐震性向上と省エネ性能の確保という2つの大きな目的があります。日本は地震が多い国であり、また、脱炭素社会の実現に向けて住宅の省エネ性能向上が求められています。そのため、政府はより厳格な基準を設け、建物の安全性や快適性を高めることを目指しています。
1. 耐震性向上の必要性
日本は地震大国であり、過去の大震災では古い建物が倒壊して甚大な被害をもたらした事例が多くあります。特に1981年以前の旧耐震基準で建てられた建物は、現在の耐震基準を満たしていないケースが多く、リフォーム時の耐震補強が推奨されています。
2. 省エネ基準の強化
政府は2050年のカーボンニュートラルを目標に掲げ、住宅の省エネ基準を強化しています。これまでは新築住宅が主な対象でしたが、今回の改正では大規模修繕や増築などの場合にも省エネ基準が適用される可能性があります。例えば、断熱性能を高めるための工事や、高効率設備の導入が求められるケースが増えるでしょう。
3. 建築確認手続きの厳格化
これまでの建築基準法では、4号特例という制度により、小規模な建築物(主に木造2階建て以下の住宅など)は建築確認の際の審査が簡略化されていました。しかし、この特例が縮小されることで、建築確認申請が必要なリフォーム工事が増えることになります。これにより、リフォームの手続きが煩雑になり、設計費用や申請コストの増加が懸念されています。
リフォームへの影響の全体像
2025年の建築基準法改正により、リフォームの計画やコストに大きな影響が出ることが予想されます。特に、建築確認申請の義務化が拡大される点、省エネ基準の適用強化、工期の長期化などが主な影響となります。
1. 建築確認申請が必要なリフォームが増加
これまで不要だったリフォームでも、確認申請が必要になるケースが増えます。法改正により、構造に関わる大規模な改修工事は新たに審査の対象となります。
例えば、屋根の形状を変更するための骨組み工事や、2階の床面積の過半を占める床板の取り外しと梁の交換作業などが含まれます。また、外壁の半分以上を取り除いて構造部材を強化する工事、建物の拡張や一部解体を伴う工事、さらには間取りを大幅に変更するために多くの内壁を撤去する工事なども対象です。
このように、建物の構造や安全性に影響を与える可能性のある大規模リフォームについては、今後建築確認申請が必要となる点に注意が必要です。
2. リフォーム費用の増加
新たな基準適用により、申請費用・設計費用の増加、追加工事の発生が予想されます。特に省エネ基準を満たすための断熱材の導入や、高性能設備の設置が義務化されると、リフォーム費用全体が上昇する可能性があります。
3. 工期が長期化する可能性
建築確認の手続きが増えることで、リフォーム開始までの期間が長くなることも予想されます。また、新基準に対応できる設計士や工務店が不足する可能性があり、施工スケジュールの遅れにも注意が必要です。
4号特例の縮小について
2025年の建築基準法改正により、これまで一部の木造住宅に適用されていた「4号特例」が大幅に縮小されます。これにより、木造2階建ての増築やリフォームでは建築確認申請が必要になるケースが増加し、手続きが複雑になる可能性があります。特に、リフォームを検討している人にとっては、これまで不要だった確認申請が求められることで、予算やスケジュールに影響が出るかもしれません。
この記事では、「4号特例」とは何か、なぜ縮小されるのか、そして新しく設けられる「新2号建築物」「新3号建築物」との違いについて詳しく解説します。
4号特例とは?
「4号特例」とは、建築基準法における特例制度の一つで、小規模な木造建築物に対して建築確認申請の一部を省略できる仕組みのことです。これにより、住宅の設計や建築手続きをスムーズに進めることができ、多くの住宅リフォームや増築が比較的自由に行える環境となっていました。
この特例の対象となる建物は、主に以下のようなものです。
- 木造2階建て以下の住宅(一般的な戸建て住宅など)
- 平屋で延床面積200㎡以下の建物
これらの建物は、これまで建築士による設計監理が前提となり、建築確認申請の際に構造審査や詳細な設計審査が省略されていました。そのため、工事の手続きが簡単で、費用を抑えつつスムーズにリフォームや増築を進めることが可能でした。
例えば、2階部分の増築や間取りの変更を行う際も、建築確認申請が不要なケースが多かったため、リフォーム会社や工務店がスピーディーに工事を進められるメリットがありました。しかし、この制度の縮小により、今後はこれまで不要だった申請が必要になり、事前の手続きや費用の負担が増えることになります。
なぜ4号特例は縮小されるのか?
2025年の法改正で4号特例が縮小される理由は、建築物の安全性向上と省エネ基準の強化にあります。これまでの制度では、建築士の設計や監理のもとで一定の安全性が確保されていましたが、以下のような課題が指摘されていました。
1. 耐震基準の不備が発生する可能性があった
日本は地震が多い国ですが、1981年以前に建築された「旧耐震基準」の建物がまだ多く残っています。リフォームの際、適切な耐震補強が行われないまま工事が進められるケースもあり、地震時の倒壊リスクが懸念されていました。特に、構造計算が省略されることによる強度不足が問題となることがありました。
2. 省エネ性能の確保が不十分だった
政府は2050年のカーボンニュートラル実現を目指しており、住宅の省エネ基準を強化しています。これまでの4号特例では、増築やリフォームの際に断熱性能やエネルギー効率のチェックが十分に行われないことがありました。そのため、リフォーム時でも省エネ基準を適用し、エコな住宅を増やす必要があると判断されたのです。
3. 違法建築や施工不良を防ぐため
建築確認の省略によって、施工ミスや基準違反が発生しやすい環境が指摘されていました。特に、耐震補強が不十分なままリフォームされるケースや、省エネ性能を満たさない改修工事が行われる可能性がありました。そのため、今後はより厳格に審査を行い、安全性と品質を確保する方針がとられています。
このような背景から、木造2階建ての住宅は4号特例の対象から外れ、建築確認申請が必要になるという変更が決定されたのです。
新2号建築物・新3号建築物とは?
4号特例が縮小されたことで、新たに「新2号建築物」「新3号建築物」という区分が導入されます。これにより、建築確認申請の手続きや必要な審査内容が変わります。
| 建物の種類 | 2024年まで(改正前) | 2025年4月以降(改正後) |
|---|---|---|
| 木造2階建て | 4号特例適用(建築確認申請不要) | 新2号建築物に分類(建築確認申請が必要) |
| 木造平屋(200㎡超) | 4号特例適用(建築確認申請不要) | 新2号建築物に分類(建築確認申請が必要) |
| 木造平屋(200㎡以下) | 4号特例適用(建築確認申請不要) | 新3号建築物(引き続き特例適用) |
1. 新2号建築物とは?
「新2号建築物」とは、これまで4号特例の対象だった木造2階建て住宅を新たに分類したものです。これにより、増築やリノベーションを行う際には、原則として建築確認申請が必要になります。特に、以下のようなリフォーム計画を検討している場合は、事前に建築士と相談することが重要です。
- 2階部分を増築する
- 耐震補強を伴う大規模リノベーションを行う
- 建物の構造に影響を与える間取り変更を行う
2. 新3号建築物とは?
「新3号建築物」は、引き続き4号特例の対象となる建築物のことを指します。具体的には、平屋(延床200㎡以下)などの小規模建築物が該当します。これらの建物については、引き続き建築確認申請が不要となるため、大きな変更はありません。
今後、リフォームや増築を検討している場合は、自分の建物が「新2号建築物」なのか「新3号建築物」なのかを事前に確認することが重要です。建築確認申請が必要かどうかを判断し、スムーズに工事を進められるよう準備を整えましょう。
2025年建築基準法改正によるリフォームへの具体的な影響
2025年の建築基準法改正により、リフォームを計画する際に新たな規制が適用されるため、事前に変更点を把握しておくことが重要です。特に、建築確認申請が必要になるケースが増え、費用や工期にも影響を及ぼすことが予想されます。
ここでは、どのようなリフォームで建築確認申請が必要になるのか、費用がどれくらい増加する可能性があるのか、そして工期への影響について詳しく解説します。リフォームを検討している方は、コストやスケジュールを適切に計画するための参考にしてください。
建築確認申請が必要になるケース
2025年の改正では、これまで建築確認申請が不要だったリフォームでも、申請が求められるケースが増えることになります。特に、建物の構造に関わる改修や増築、スケルトンリフォームなどが対象です。
ここでは、建築確認申請が必要になる代表的なリフォームの種類について詳しく見ていきましょう。
大規模な修繕・模様替え
「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」とは、建物の主要な構造部分(柱・梁・壁・床など)に影響を及ぼす改修を指します。具体的には、以下のような工事が該当します。
- 耐震補強を目的とした壁や柱の補修・交換
- 間取り変更に伴う構造部の撤去・新設
- 屋根や外壁の大規模な改修(耐震や断熱性能向上を伴うもの)
例えば、耐震性を向上させるために柱や梁を補強する場合や、壁を取り払ってリビングを広くするような工事では、建築確認申請が必要になります。これまでは申請不要だったリフォームでも、建築基準法に適合しているかの審査が行われるため、設計段階から確認しておくことが大切です。
リフォーム費用への影響
建築基準法改正によって、リフォームの際の費用負担が増加することが予想されます。特に、建築確認申請にかかる手数料や設計費用、省エネ基準適合のための追加費用、工期の長期化によるコスト増加が懸念されます。
省エネ基準適合のための追加費用
改正後のリフォームでは、省エネ基準を満たすことが求められるため、断熱材の追加や窓の性能向上といった改修が必要になります。これにより、追加の工事費用が発生する可能性が高いです。
例えば、既存の住宅を省エネ基準に適合させるためには、以下のような工事が必要になる場合があります。
- 断熱材の追加施工
- 高性能サッシや窓ガラスの交換
工期の長期化による費用
建築確認申請が必要になることで、リフォームの工期が長引く可能性があります。これにより、仮住まいの費用や追加の人件費が発生することも考えられます。
例えば、スケルトンリフォームを行う場合、申請手続きだけで1〜2カ月かかることもあります。そのため、工事期間中の家賃負担が発生する場合は、その分の予算も考慮する必要があります。
リフォーム時の注意点と対策
2025年の建築基準法改正により、リフォームを検討する際にはこれまで以上に慎重な計画が求められます。ここでは、法改正後の注意すべきポイントやコスト削減の方法について詳しく解説します。
法改正後にリフォームする場合の注意点
2025年4月以降にリフォームを行う場合、建築確認申請の義務が発生するケースが増えるため、事前に準備を整えることが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
建築確認申請に対応できる業者の選び方
改正後は、リフォームの際に建築確認申請が必要になるケースが増えます。そのため、建築確認申請の実績がある業者を選ぶことが重要です。
- 一級建築士事務所や建築確認申請の経験が豊富な工務店を選ぶ
- 過去に耐震改修や省エネリフォームを手掛けた実績があるかを確認する
- 施工だけでなく、申請手続きのサポートを行ってくれるかをチェックする
特に、耐震補強を伴うリフォームや増築を行う場合は、法規制の理解がある業者に依頼することでスムーズに進められます。
既存不適格建築物への対応
既存不適格建築物とは、建築当時の基準では適法だったが、その後の法改正で現行基準に適合しなくなった建物を指します。こうした建物のリフォームでは、特に耐震や省エネ基準への適合が求められることが多く、以下の点に注意が必要です。
- 耐震診断を行い、補強工事が必要か確認する
- 断熱性能を向上させるための追加工事を見積もる
- 改修内容によっては現行基準に適合させる義務が生じる可能性があるため、事前に確認する
再建築不可物件における注意点
再建築不可物件とは、現行の建築基準法で定められた接道義務を満たしていないため、新たに建築できない物件です。こうした物件のリフォームには以下のような制約があります。
- 建築確認申請が必要なリフォームを行うと、適合義務が発生する可能性がある
- 大規模改修では、現行基準に適合させる必要があり、コストが増加する
- 接道義務を満たしていない場合、増築は不可となるケースが多い
再建築不可物件のリフォームを検討する場合は、行政や専門家と事前に相談し、法規制の範囲内で可能な工事を検討することが重要です。
費用を抑えるための対策
法改正後のリフォームは、建築確認申請や耐震・省エネ基準適合のための追加費用が発生する可能性があるため、コスト削減策を検討することが大切です。
補助金・助成金の活用
耐震改修や省エネリフォームに関する補助金・助成金を活用することで、費用負担を軽減できます。
- 「子育てグリーン住宅支援事業」 … 省エネ性能の向上を目的とした制度で最大160万円の補助金
- 「先進的窓リノベ2025事業」 … 高性能な断熱窓への改修を補助する制度で、最大200万円の補助金
- 地方自治体独自の補助金 … 地域ごとに耐震改修・省エネリフォームに関する補助制度あり
リフォーム計画を立てる際は、国や自治体の補助金制度を事前に調査し、適用可能なものを活用することで、トータルコストを抑えられます。
関連記事:【2025年版】子育てグリーン住宅支援事業とは?補助金活用で省エネ住宅を実現!
関連記事:「先進的窓リノベ事業2025」とは?補助金でお得に窓リフォーム!
減築などコンパクトなリフォームの検討
リフォーム費用を抑える方法として、減築(建物の一部を撤去して小さくする工事)を検討するのも有効です。
- 固定資産税の軽減につながる(延床面積が減少するため)
- メンテナンス費用が削減できる(居住スペースが減ることで、将来的な修繕費も抑えられる)
- 耐震性能の向上が期待できる(建物の重量が軽くなることで耐震性が向上)
減築のほか、間取りを変更せずに断熱性能を向上させるリフォームを選択することで、追加の建築確認申請が不要になる場合もあります。
まとめ:2025年建築基準法改正に備えて
2025年の建築基準法改正により、リフォームにおける手続きの厳格化やコスト増加が予想されます。特に4号特例の縮小により、小規模な工事でも建築確認申請が必要になるケースが増えるため、これまで以上に計画的な準備が求められるでしょう。
しかし、適切な対策を講じることで、スムーズにリフォームを進めることは十分可能です。法改正前にリフォームを済ませるか、補助金を活用してコストを抑えるかなど、自分に合った選択肢を検討しましょう。また、信頼できる施工業者と早めに相談することも重要です。
リフォームは「快適な住まいを実現する大切なプロジェクト」です。しっかり情報収集し、最適なタイミングで計画を立てることで、後悔のないリフォームを実現しましょう。これからの家づくりに役立つ情報を随時発信しているので、ぜひ他の記事もチェックしてみてください!
設計工房枻は、設計から施工まで一貫して行う「設計事務所×工務店」です。
新築やリフォームをご検討中の方は、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
ご相談、資料請求は下記バナーをクリック!