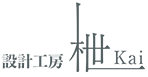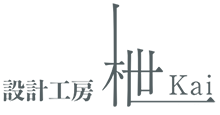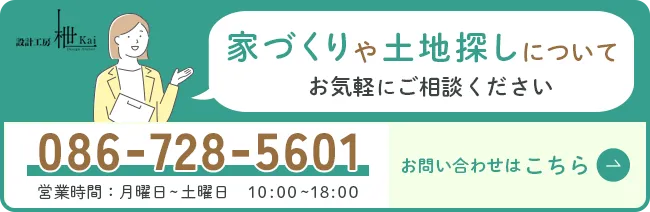マイホーム計画を進める中で、「長期優良住宅」という言葉を目にすることが多いのではないでしょうか。住宅展示場やハウスメーカーのカタログでよく見かけるこの言葉、なんとなく「良い住宅」というイメージはあるものの、具体的にどんな制度なのか、どんなメリットがあるのか、そしてデメリットはないのか…多くの方が疑問を抱えています。
日本の住宅は平均寿命が約30年と言われ、欧米の100年以上と比べて非常に短いのが現状です。数千万円という大きな買い物にもかかわらず、資産価値が急速に下がっていくことに不安を感じている方も多いでしょう。
「せっかく購入するなら、長く安心して住める家がいい」「将来売却する時にも価値が残っている家がいい」という願いは、誰もが持つ自然な気持ちです。
そこで注目されているのが「長期優良住宅」制度です。この記事では、長期優良住宅の基本的な概念から認定基準、税制優遇などの具体的なメリット、そして見落としがちなデメリットまで、2025年最新情報をもとに徹底解説します。どんな人に向いているのか、後悔しないための検討ポイントもご紹介しますので、マイホーム計画中の方はぜひ参考にしてください。
長期優良住宅とは?【長く快適に暮らせる住まいの認定制度】
長期優良住宅とは、耐久性や環境性能、維持管理のしやすさなどの一定基準を満たし、長期にわたり良好な状態を維持できると認定された住宅のことを指します。2009年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、認定制度が設けられました。
この制度の目的は、従来の「建てては壊す」住宅市場から脱却し、質の高い住宅を長く使い続けることで、環境負荷の軽減や住まいの資産価値向上を促すことにあります。日本では住宅の平均寿命が30年程度と短く、欧米諸国の50~60年と比べると大きな差があります。そのため、長期優良住宅の認定制度を活用することで、住宅の長寿命化を進めることが求められています。
長期優良住宅の背景と制度の必要性
なぜ長期優良住宅が必要なのか、その背景には日本の住宅事情の課題があります。
- 住宅の寿命が短い
日本の住宅は30~40年程度で建て替えられるケースが多く、これにより大量の廃棄物が発生し、環境負荷が大きくなっています。欧米のように50年以上住み続けられる家づくりが求められています。 - 資産価値の低下が早い
一般的に、日本の住宅は築年数が経つにつれ価値が急速に下がります。しかし、長期優良住宅は高い品質を維持できるため、中古市場でも価値を保ちやすくなります。 - 環境負荷の軽減
建て替えの頻度が高いと、建設時のCO₂排出や廃材の処理による環境負荷が増加します。長期優良住宅は長く住めるため、結果的に環境負荷の軽減につながります。
長期優良住宅の8つの主な認定基準・条件

長期優良住宅の認定を受けるには、国土交通省が定める基準を満たさなければなりません。特に新築住宅の場合、以下の8つの基準が重要です。それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
① 劣化対策
長く住み続けるためには、住宅の耐久性を確保することが不可欠です。そのため、劣化対策として以下の基準が設けられています。
- 数世代にわたって使用できる構造・躯体であること
- 木造住宅の場合、主要な構造部分の耐久性を3世代(75〜90年)程度維持できる対策が施されていること
- 鉄筋コンクリート造の場合、適切な防錆・防湿対策がされていること
例えば、木造住宅では防腐・防蟻処理が義務付けられており、床下や天井裏の点検・メンテナンスのしやすさも求められます。これにより、住宅の劣化を防ぎ、長く快適に住める住環境が確保されます。
② 耐震性
日本は地震が多い国のため、長期優良住宅には高い耐震性が求められます。基準としては、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 耐震等級2以上(建築基準法の1.25倍の耐震性能)
- 免震・制震構造を採用し、地震時の揺れを軽減する工夫がされていること
これにより、地震が発生した際でも建物の倒壊リスクを低減し、長く安心して住める住宅を実現します。
③ 省エネルギー性
省エネ性能も、長期優良住宅において重要な基準の一つです。基準を満たすためには、以下の条件をクリアする必要があります。
- 断熱性能が一定以上であること(断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上)
- エネルギー消費量を削減する設備(高効率給湯器・太陽光発電など)を導入すること
特に、高気密・高断熱の住宅設計が求められ、冷暖房エネルギーの消費を抑えることがポイントとなります。結果として、光熱費の削減にもつながります。
④ 維持管理・更新の容易性
住宅を長期間使用するためには、設備の交換やメンテナンスがしやすい設計であることが求められます。そのため、以下の条件をクリアする必要があります。
- 配管類が容易に交換できる構造であること
- 点検口が設けられ、適切な維持管理ができること
例えば、給排水管が壁内に埋め込まれていると交換が難しくなりますが、メンテナンスしやすい配管設計であれば、将来的な修繕コストを抑えることができます。
⑤ 居住環境
住宅が周囲の環境と調和し、良好な住環境を形成できることも認定基準の一つです。具体的には、以下のような条件が求められます。
- 都市計画や景観条例に適合していること
- 住民の生活環境を損なわない配慮がされていること
たとえば、住宅密集地での建築では日照や通風を確保する設計が求められることがあり、地域の条例に基づいた計画が必要になります。
⑥ 住戸面積
快適な居住空間を確保するために、一定の住戸面積が必要とされます。基準は以下の通りです。
- 戸建て住宅:75㎡以上
- 共同住宅(マンション等):55㎡以上
これにより、狭すぎる住宅の建築を防ぎ、適切な居住空間を確保することができます。特にファミリー向けの住宅では、この基準を大幅に上回る広さが推奨されることもあります。
⑦ 維持保全計画
長期優良住宅に認定されるためには、住宅の長寿命化を前提とした維持保全計画を策定する必要があります。この計画には、以下の内容が含まれます。
- 定期的な点検・メンテナンスの計画(少なくとも10年ごと)
- 修繕やリフォームの実施予定の記録
例えば、外壁や屋根は10年ごと、給排水設備は5年ごとに専門業者による点検を行うといった具体的なスケジュールを定めます。次に、補修や交換の時期・内容・実施者についても明記します。さらに、これらの記録の作成方法や保存方法についても計画に含める必要があります。
長期優良住宅の認定を受けた後も、この計画に基づいた維持管理を行う義務があります。これにより、住宅の品質を長期間維持し、将来的な資産価値を高めることができます。
⑧ 災害配慮
長期優良住宅の認定基準として、2022年に新たに追加されたのが「災害配慮基準」です。近年の気候変動による自然災害の増加を背景に、住宅の防災性能を高めることで、長期にわたる安全な居住環境を確保することを目的としています。主な基準は以下の通りです。
- 水害や土砂災害リスクが高い地域では適切な対策を講じること
- 避難経路や防災設備の確保
例えば、ハザードマップを活用し、災害リスクの少ない土地を選ぶことも重要です。
長期優良住宅のメリット

長期優良住宅に認定されると、税制優遇や金利引き下げなどのさまざまなメリットが受けられます。特に住宅ローン減税や固定資産税の軽減は、経済的な負担を大きく軽減するポイントです。また、地震保険の割引や住宅の資産価値向上など、長期的に見ても多くの利点があります。ここからは、これらのメリットを詳しく解説していきます。
税制上のメリット
長期優良住宅は、税制優遇措置が充実している点が大きな魅力です。住宅購入時や所有時に適用される減税措置により、数十万円~数百万円の節税が可能になることもあります。
住宅ローン減税(所得税)の控除限度額拡大
住宅ローン減税とは、住宅を購入した際に支払った所得税の一部を控除できる制度です。長期優良住宅の場合、通常の住宅よりも控除額が拡大され、より多くの税負担を軽減できます。
【控除額の比較】
| 住宅の環境性能等 | 控除率 | 借入限度額 | 控除期間 | 床面積要件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年入居 | 令和7年入居 | ||||
| 省エネ 基準適合住宅 | 0.7% | 子育て世帯・若者夫婦世帯(1):4,000万円 その他の世帯:3,000万円 | 3,000万円 | 13年 | 50㎡ ※新築住宅の場合、令和6年までに建築確認:40㎡ (所得要件:1,000万円) |
| 長期優良住宅 | 0.7% | 子育て世帯・若者夫婦世帯(1):5,000万円 その他の世帯:4,500万円 | 4,500万円 | 13年 | |
※2025年3月時点 参照:国土交通省
上記のように、長期優良住宅は省エネ基準適合住宅よりも借入限度額が大きいため、より多くの控除を受けることができます。
投資型減税(所得税)
住宅ローンを利用しない場合でも、長期優良住宅なら「投資型減税」が適用されます。これは、住宅の性能向上のための投資額の10%を所得税から控除できる制度です。
例えば、長期優良住宅の建築費用が3,000万円の場合、最大65万円の所得税控除を受けられる可能性があります。これは、ローンを利用しない現金購入者にとっても大きな節税効果をもたらします。
登録免許税の税率引き下げ
住宅を取得する際、所有権を登記するための登録免許税が発生します。長期優良住宅では、この税率が軽減されます。
| 登録の種類 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.15% | 0.1% |
| 所有権移転登記 | 0.3% | 0.2% |
例えば、3,000万円の新築住宅を購入した場合、登録免許税が通常45,000円かかるところ、長期優良住宅なら30,000円に軽減されます。
不動産取得税の控除額増額
不動産取得税は、住宅を購入した際に課せられる税金ですが、長期優良住宅の場合、控除額が拡大されます。
- 一般住宅:控除額1,200万円
- 長期優良住宅:控除額1,300万円
つまり、長期優良住宅なら100万円分の税金が非課税となり、さらに負担が軽減されます。
固定資産税の減税期間延長
固定資産税は、住宅を所有している限り毎年発生する税金です。長期優良住宅の場合、この固定資産税の減税期間が延長されます。
| 住宅の種類 | 減額率 | 減税期間 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 1/2 | 3年間 |
| 長期優良住宅 | 1/2 | 5年間 |
例えば、年間固定資産税が10万円の場合、
- 一般住宅の場合:1~3年目が5万円、4~5年目が10万円、合計35万円
- 長期優良住宅の場合:1~5年目で合計25万円
このように、長期優良住宅なら5年間で合計10万円の節税が可能になります。
金利優遇
長期優良住宅を購入すると、住宅ローンの金利優遇を受けられる場合があります。
住宅ローンの金利引き下げ(フラット35Sなど)
長期優良住宅は、住宅ローンの金利優遇を受けることができる点でも大きなメリットがあります。特に、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】を利用する場合、金利が一定期間引き下げられる「【フラット35】S」の対象となります。
【フラット35】Sには、住宅の省エネルギー性や耐震性に応じた金利引き下げメニューがあり、長期優良住宅はその条件を満たしやすい特徴があります。具体的な金利引き下げ内容は以下の通りです。
| 金利引き下げメニュー | 金利引き下げ期間 | 金利引き下げ幅 |
|---|---|---|
| 【フラット35】S(ZEH) | 当初5年間 | 年▲0.75% |
| 【フラット35】S(金利Aプラン) | 当初5年間 | 年▲0.50% |
| 【フラット35】S(金利Bプラン) | 当初5年間 | 年▲0.25% |
長期優良住宅の場合、【フラット35】維持保全型と【フラット35】S(金利Aプラン)を併用することが可能で、その場合、当初5年間は最大年0.75%の金利引き下げが適用されます。
さらに、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たした長期優良住宅であれば、【フラット35】維持保全型と【フラット35】S(ZEH)を併用することができ、当初5年間の金利引き下げ幅は最大年1.00%となります。
これにより、数百万円単位での利息軽減が見込めるため、住宅ローンを利用する方にとっては非常に大きなメリットとなるでしょう。特に、省エネ性能の高い住宅を検討している場合、長期優良住宅の認定を受けることで、金利面でも有利な条件を得ることができます。
フラット50の利用
長期優良住宅は、「フラット50」という最長50年の住宅ローンを利用できる可能性があります。通常の住宅ローンよりも長期間の返済が可能になり、月々の返済額を抑えやすいのが特徴です。
地震保険料の割引
長期優良住宅は、地震に強い設計が求められるため、地震保険の割引も適用されます。耐震等級2なら30%割引、耐震等級3なら50%割引となり、年間の保険料を大幅に抑えることができます。
その他のメリット
長期優良住宅の魅力は、税制優遇や金利引き下げだけではありません。長期的な視点で見ると、住宅の資産価値の維持や居住性の高さなど、金銭的な価値に換算しにくい大きなメリットがあります。ここでは、長期優良住宅を選ぶことで得られるその他の重要なメリットについて解説します。
住宅の資産価値が向上しやすい
長期優良住宅は、一般的な住宅よりも資産価値が落ちにくいのが特徴です。認定を受けた住宅は市場でも評価されやすく、将来売却する際も有利になります。
長く安全・快適に暮らせる
認定基準を満たしているため、耐久性・耐震性・省エネ性に優れた住まいを実現できます。長期間にわたって安心して住み続けられる住宅であることが、認定制度によって担保されています。
長期優良住宅のデメリット・注意点
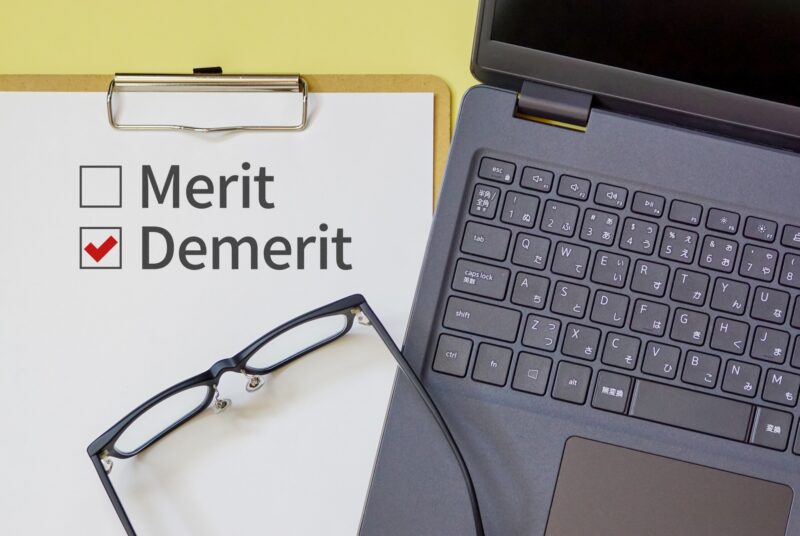
長期優良住宅には多くのメリットがありますが、その一方でデメリットや注意点もあります。特に、申請にかかる手間や費用、建築費の増加、入居後の維持保全義務などは、事前に理解しておくことが大切です。ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
申請にかかる手間と費用
長期優良住宅の認定を受けるためには、専門的な知識と時間が必要です。申請書類の作成や審査機関とのやり取りなど、煩雑な手続きが発生します。また、認定を受けるための費用もかかります。これらの手間と費用は、長期優良住宅の大きなデメリットと言えるでしょう。
例えば、認定申請の手数料は、住宅の規模や構造によって異なりますが、十万円程度かかる場合があります。また、申請書類の作成を専門家に依頼する場合は、さらに費用がかさむこともあります。
建築費が割高になる可能性
長期優良住宅の認定を受けるためには、通常の住宅よりも高品質な建材や設備を使用する必要があります。そのため、建築コストが割高になることが多いのが現実です。
例えば、耐震性能の向上にはより強固な基礎工事や耐震補強材が必要になりますし、省エネルギー性能の確保には高性能な断熱材や省エネ設備の導入が求められます。これにより、建築費が通常の住宅より10~20%程度高くなるケースもあります。
ただし、補助金や税制優遇を活用することで、コスト負担を軽減することは可能です。長期的に見れば、メンテナンス費用や光熱費の削減にもつながるため、トータルコストで判断することが重要です。
入居後の維持保全の義務
長期優良住宅では、一定の維持管理・メンテナンスを義務付けられている点もデメリットとして挙げられます。通常の住宅よりも手間がかかるため、しっかりと計画を立てることが必要です。
定期的な点検・メンテナンス
長期優良住宅の所有者は、定期的に住宅の点検を行い、必要に応じて修繕を実施する義務があります。例えば、外壁や屋根の劣化点検は10年ごと、配管のメンテナンスは20年ごとに実施することが推奨されています。
点検の費用は規模や内容によって異なりますが、1回あたり数万円~10万円程度が一般的です。メンテナンスを怠ると、住宅の価値が下がるだけでなく、認定のメリットを十分に活かせなくなる可能性もあります。
維持保全計画の作成と実施
認定を受けた住宅は、維持保全計画を作成し、それに基づいて適切な管理を行う義務があります。この計画には、点検スケジュールや修繕計画、使用する建材の種類などが含まれます。
特に、将来的に売却を考えている場合は、維持保全計画に沿った管理が求められ、買い手に対して適切な住宅管理が行われていることを証明する資料として活用できます。
記録の作成・保存・報告の義務
点検や修繕を行った場合、その内容を記録し、一定期間保存しておく義務があります。これには、点検結果の報告書や修繕履歴の管理が含まれます。自治体によっては、定期的な報告が求められることもあるため、しっかりと対応することが重要です。
長期優良住宅はどんな人におすすめ?【後悔しないための検討ポイント】
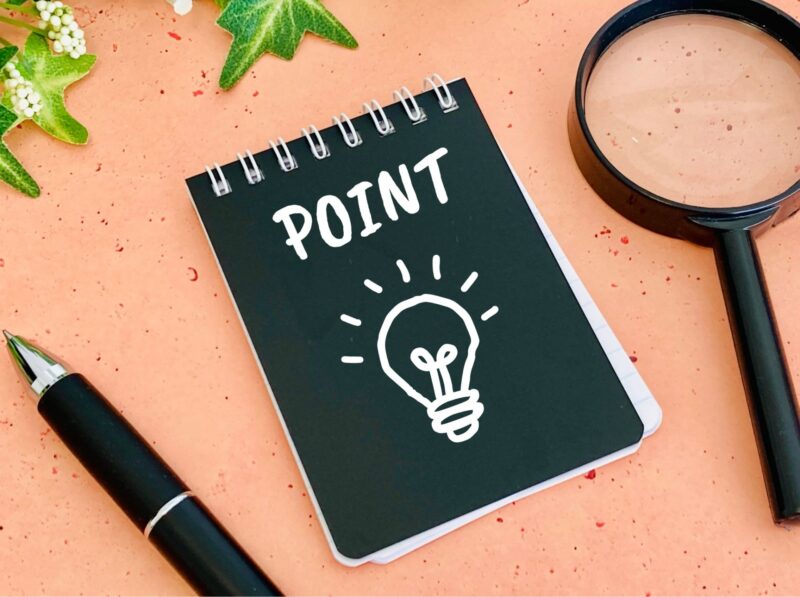
長期優良住宅は、耐震性や省エネ性に優れ、税制優遇や住宅ローンの金利引き下げといったメリットがあります。しかし、すべての人に適しているわけではなく、ライフスタイルや将来の計画に合わせた選択が重要です。ここでは、長期優良住宅がどのような人に向いているのか、具体的な検討ポイントとともに解説します。
長期にわたり安心して住みたい方
長期優良住宅は、長く快適に住めるよう設計された高品質な住宅です。耐震性能や劣化対策が施されているため、一般的な住宅よりも長寿命で、頻繁な修繕の必要が少ないのが特徴です。
例えば、耐震性については、耐震等級2以上(建築基準法の1.25倍の強度)が求められ、地震に強い構造になっています。また、劣化対策等級3(3世代にわたり住める水準)を満たすことで、柱や梁の劣化が抑えられます。これにより、築年数が経っても安心して住み続けられる住宅が実現できます。
さらに、長期優良住宅は定期的なメンテナンスを前提としているため、適切な維持管理を行うことで住宅の資産価値を維持しやすい点も魅力です。
税制優遇や金利優遇を受けたい方
長期優良住宅を取得すると、各種の税制優遇や住宅ローンの金利引き下げが受けられるため、住宅購入のコストを抑えたい方にもおすすめです。
【税制優遇の例】
- 住宅ローン控除:借入限度額が最大4,500万円に増額し、控除額が拡大
- 固定資産税の軽減:新築から5年間は1/2に減額(一般住宅は3年間)
- 不動産取得税の軽減:課税標準額の控除額が一般住宅の1,200万円 → 1,300万円に増額
また、住宅金融支援機構の【フラット35】では、長期優良住宅向けの金利優遇制度が適用されます。例えば、【フラット35】S(金利Aプラン)と維持保全型を併用することで、当初5年間の金利が年0.75%引き下げられます。さらにZEH水準の住宅なら、最大1.00%の引き下げも可能です。
こうした制度を活用すれば、住宅取得の負担を軽減しつつ、より高品質な住まいを手に入れることができます。
地震に強く、省エネ性能の高い家に住みたい方
長期優良住宅は、高い耐震性能と省エネ性能を兼ね備えた住宅です。これらの性能は、住宅の安全性や快適性を大きく向上させるため、特に地震の多い地域に住んでいる方や、光熱費を抑えたい方に適しています。
例えば、長期優良住宅の省エネ基準として、断熱等性能等級5以上が求められます。これは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)レベルの高断熱性能を確保することを意味し、冷暖房費を削減しながら快適な室内環境を維持できます。
また、地震対策としては、耐震等級2以上が必須で、さらに耐震等級3(消防署や警察署と同等の強度)を目指すことで、より安全な住まいを実現できます。こうした性能により、万が一の災害時にも家族を守れる家になるため、安心して暮らせる住宅を求める方におすすめです。
ZEH水準については、関連記事「ZEH(ゼッチ)とは?未来の省エネ住宅の基準・費用・メリットを徹底解説」で解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
将来的に住宅を売却・相続する可能性がある方
長期優良住宅は、将来的に売却や相続を考えている方にも適した選択肢です。なぜなら、築年数が経っても価値が落ちにくく、中古市場で評価されやすいためです。
通常の住宅では、築20~30年経過すると市場価値が大幅に下がることが一般的ですが、長期優良住宅の場合、維持管理がしっかりされていることが証明できれば、資産価値を維持しやすいのが特徴です。また、認定住宅は中古住宅市場での評価が高く、売却時に有利になる可能性があります。
さらに、相続時にもメリットがあります。長期優良住宅の固定資産税の軽減措置が適用されることで、相続後の負担を軽減できる点も魅力です。家族の将来を見据えた住宅選びを考える方には、特におすすめの選択肢といえるでしょう。
長期優良住宅を検討する際のポイント
長期優良住宅を選ぶ際には、住宅の性能だけでなく、施工会社の信頼性や資金計画、維持管理の負担についても慎重に考える必要があります。
実績のある住宅会社を選ぶ
長期優良住宅の認定を受けるには、基準を満たした設計・施工が求められるため、実績のある住宅会社を選ぶことが重要です。施工実績が少ない会社では、申請手続きに不慣れなケースもあるため、過去の認定実績を確認することがポイントです。
また、アフターサービスや長期保証の有無もチェックしましょう。長期的な視点で安心して住める住宅を提供しているかどうかを判断することが大切です。
資金計画をしっかり立てる
長期優良住宅は、一般的な住宅よりも建築費が高くなる傾向があります。そのため、補助金や税制優遇を活用しつつ、無理のない資金計画を立てることが重要です。
例えば、【フラット35】の金利引き下げや、ZEH補助金などを組み合わせることで、負担を抑えながら高性能な住宅を手に入れることができます。事前に住宅ローンのシミュレーションを行い、総額でいくらかかるのかを明確にしておきましょう。
住宅補助金については、関連記事「【2025年住宅補助金】4つの住宅省エネキャンペーンを徹底解説!」で解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
維持管理の負担も考慮する
長期優良住宅は、維持保全計画の作成や定期的なメンテナンスが義務付けられているため、管理の手間やコストについても考慮する必要があります。
例えば、10年ごとの外壁・屋根の点検や、設備の交換費用などが発生するため、将来的なランニングコストを見積もっておくことが大切です。特に、メンテナンス費用を抑えたい場合は、耐久性の高い建材やメンテナンスフリーの外装材を選ぶのも一つの方法です。
まとめ【長期優良住宅で長く快適な暮らしを実現】
長期優良住宅は、耐久性・省エネ性・居住性に優れ、長く快適に住み続けられる住宅です。税制優遇や住宅ローンの金利引き下げといった経済的なメリットも多く、将来の資産価値を守るうえでも魅力的な選択肢といえます。
しかし、その一方で、申請や維持管理の手間、建築コストの増加といった注意点もあります。長期優良住宅を検討する際は、これらのポイントを理解し、自分にとって最適な住まいの条件を見極めることが大切です。
家は一生に一度の大きな買い物だからこそ、しっかりと知識をつけ、後悔のない選択をしたいですよね。これから家を建てる・購入する方は、長期優良住宅を選択肢の一つとして検討し、自分や家族にとって最適な住まいを実現しましょう!
設計工房枻は、設計から施工まで一貫して行う「設計事務所×工務店」です。
新築やリフォームをご検討中の方は、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
ご相談、資料請求は下記バナーをクリック!